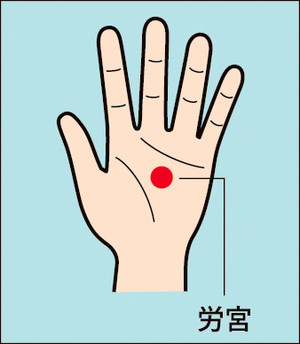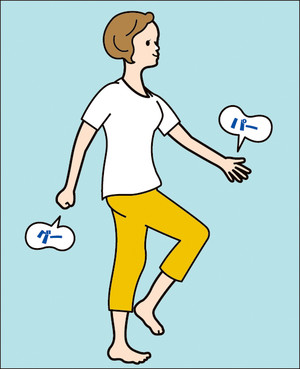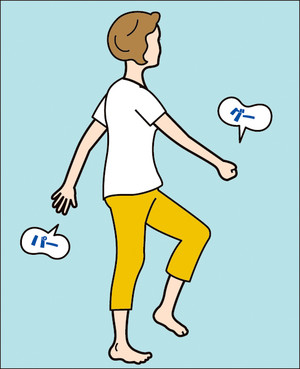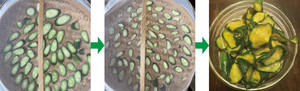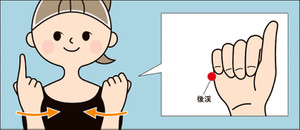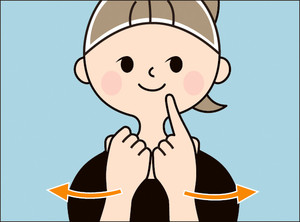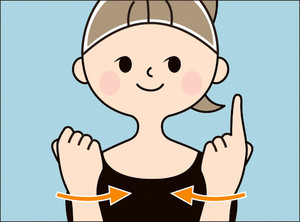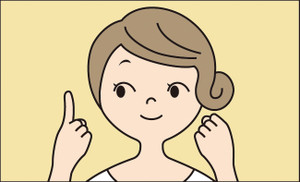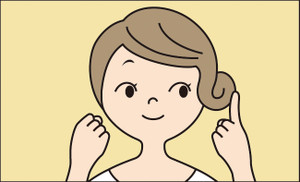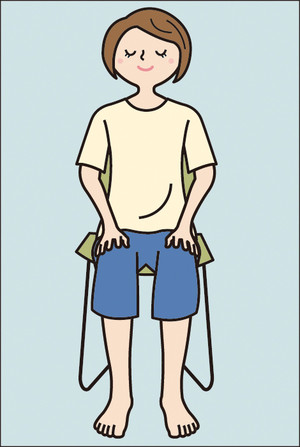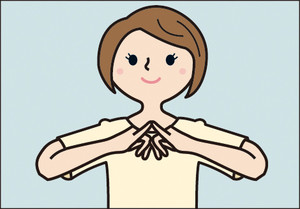富士山の初冠雪
気象予報士●檜山靖洋
甲府の気象台から、富士山の初冠雪が観測される日は平年10月2日です。初冠雪とは、山頂付近が雪で覆われた状態を麓の気象台から寒候期(10〜3月)に入り初めて確認できることです。山に雪が積もっても、雲に隠れて見えないと初冠雪にはなりません。晴れてきて山頂付近を確認できた日が観測日となります。
富士山には一年中雪が降ります。そのため、いつがシーズン初めの雪かを判定するための条件があります。山頂の日ごとの平均気温がその年最も高くなった日を境目とし、気温が下がり始めてから初めて山の雪化粧を確認できた日が初冠雪となります。初冠雪の発表後に気温が上がり、その年の最も高い気温を上回った場合、一度発表された初冠雪は取り消され、あらためて気温が下がり始めてから観測します。2021年は9月7日に初冠雪が観測されましたが取り消され、9月26日に初冠雪となりました。一年中雪が降る富士山ならではの条件ですね。
気象予報士・防災士
檜山 靖洋(ひやま やすひろ)
1973年横浜市生まれ。
明治大学政治経済学部政治学科を卒業後、印刷会社に就職。
1999年に気象予報士を取得し気象会社へ転職。
2005年からNHKの気象キャスターに。
朝のニュース番組「おはよう日本」の気象情報に出演中。